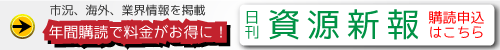一般廃棄物
家庭ごみ処理の歴史
「井戸の茶碗」や「らくだ」など、古典落語には「屑ぃ、お払い」の売り声とともに町内を回り家庭から不用品を買い集める「屑屋」という職業が登場する噺は多いが、近世、日本では古紙や古着はもちろん、し尿や?涙にいたるまで、ありとあらゆるものが自由経済のなかでリユース・リサイクルされていた。そのほか、全く市場性のない「ごみ」は沿岸地域や川、湿地などに埋立処分されるのが一般的だった。
そういったなか、行政機関が家庭ごみ処理に積極的に関与するようになったのは、1900年(明治33年)に制定された「汚物掃除法」が始まりとされる。開国により海外との行き来が活発になり、都市部の人口も急激に増加したため、ペストなどの伝染病が流行。この対策として、国はごみの収集・処分を市町村の義務として位置付け、ごみ収集業者を行政の管理下に置くことで公衆衛生の強化に努めた。なお、同法では、各家庭で蓋付の容器を用意のうえ、「生ごみ」、「可燃ごみ」、「不燃ごみ」の3種類に分類するよう定めていた。「なるべく焼却すること」としていた「可燃ごみ」は野焼きされるのが主流で、本格的な清掃工場の普及は昭和初期まで待たなければならない。
1926年(昭和5年)の法改正で一時は義務付けられたごみの焼却だったが、翼賛体制のなか、清掃工場の食品工場、パルプ工場、軍需工場などへの転用が相次ぎ、1935年(昭和16年)の改正では、焼却義務が外される。また、この時期は食糧難や資源確保の観点からごみ減量が叫ばれ、婦人会主導による町会単位での古紙や古着、金属類といった再生資源物の回収が盛んに行われており、ここに現在の集団回収のルーツの一端を見ることが出来る。
「一般廃棄物」という考え方
戦後、再び国として家庭ごみ処理のあり方を整備したのが1954年(昭和29年)制定の「清掃法」。これまでの市町村がごみの収集・処分を行う仕組みに加えて、国と都道府県が財政的・技術的援助を行うこと、住民に対しても市町村が行う収集・処分への協力義務を課すことなどを定めた。一方で、戦後復興は目覚ましく、急速に工業化が進むなか、新たな問題が発生してくる。事業者の排出するごみ(以下、「事業ごみ」)の不法投棄が多発し、公害問題が表面化していったのだ。
「公衆衛生の向上」を目的に家庭ごみ処理に主眼を置いて設計された従来の「清掃法」では、この事態に対処できず、1970年(昭和45年)の「公害国会」で、今日にまで続く「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(「廃棄物処理法」、「廃掃法」などと略される)が新たに制定される。この法では法の目的に「生活環境の保全」を追加し、「廃棄物」という概念を導入。さらに、事業ごみのうち20種類を排出事業者が処理責任を有する「産業廃棄物」として定義する。その対となる「一般廃棄物」は、「産業廃棄物」以外の廃棄物を指し、従来と同じく市町村が処理責任を有するものとして改めて定義し直した。
他方で、現実的には廃掃法制定以前は大部分の事業ごみを市町村が収集・処理していたことから、「産業廃棄物」以外の事業ごみは便宜的に「事業系一般廃棄物」と称されるようになり、引き続き市町村が処理責任を有することとなっている。
このように一般廃棄物は、歴史的に市町村に処理責任があると明確に規定されてきており、市町村に与えられている法解釈の幅が広いため、「事業系一般廃棄物」の該当範囲や「専ら物」の解釈など、市町村ごとに考え方が大きく異なる部分も多い。
また、近年はゴミ出し時間や清掃工場の受入時間の柔軟化の必要性、「遺品整理」や「不用品回収」に関する制度整備、廃棄物の少量多品種化への対応、温暖化対策の観点から収集運搬効率化の必要性など、社会構造やライフスタイルの変化と法制との齟齬が多く指摘されているところだ。